遺言書を安全・確実に保管!自筆証書遺言書保管制度を徹底解説
相続に関する相談件数は年々増加し、長期化する家族間トラブルも目立ちます。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で「紛失・改ざん・形式不備」のリスクがつきものでした。こうした課題を一挙に解決できるのが2020年に始まった 自筆証書遺言書保管制度 です。
本記事では制度を使いこなすためのポイントを、初心者向けにわかりやすくまとめました。

はじめに
相続トラブルを防ぐカギは「遺言書」の作成と安全な保管です。適切な遺言書は相続争いを防ぐだけでなく、相続手続きの負担を軽減し、場合によっては相続税の節税効果も期待できます。
本稿では 3,900円で法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」 を中心に、制度概要から手続き方法、よくある疑問まで徹底解説します。
目次
- 遺言書とは何か?その必要性と種類
- 自筆証書遺言の従来の課題
- 自筆証書遺言書保管制度とは?
- 保管制度の利用方法を具体的に解説
- 制度利用時の注意点・よくある質問(FAQ)
- 制度が向いている人・向いていない人
- 最新情報
- まとめ・CTA
【重要な免責事項】 本記事は 2025年6月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当方は責任を負いません。【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
1. 遺言書とは何か?その必要性と種類
| 種類 | 作成・保管方法 | 費用目安 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自筆(財産目録のみ PC 可)/自宅または 法務局保管 証人:不要、検認※1:必要(保管制度なら不要) | 作成:無料 保管制度:3,900円 | 紛失・改ざんリスク→保管制度で回避/形式不備に注意 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で口述 →公証人が作成・原本保管 証人:2名以上、検認※1:不要 | 財産額に応じた公証人手数料(数千~数万円) | 証拠力が高く安全/費用と証人確保が必要 |
| 秘密証書遺言 | パソコン等で作成可 →封印し公証役場で手続き 証人:2名以上、検認※1:必要 | 公証役場手数料 11,800円~(封印代等別途) | 内容の秘匿性あり/手続きが複雑で検認必須 |
※1 検認 = 家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し改ざんを防ぐ手続き。遺言の有効性を判断するものではありません。
2. 自筆証書遺言の従来の課題
- 紛失・隠匿のリスク — 火災・災害・第三者による持ち去りで原本が失われるリスク
- 改ざん・偽造の可能性 — ページの差し替えや押印の変更により真正性が争点となるケース
- 形式不備による無効 — 署名・日付・押印の欠落や不備による遺言無効の判例が多数存在
- 検認手続きの負担 — 相続発生後、家庭裁判所での手続きに数週間から数か月を要する
3. 自筆証書遺言書保管制度とは?
制度概要
2020年7月に施行された制度で、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を原本と画像データで長期保管し、相続開始後の検認手続きを不要にする公的サービスです。
主なメリット
| メリット | 詳細な解説 |
|---|---|
| 紛失・改ざん防止 | 原本50年、画像データ150年の長期保管により、紛失・改ざんリスクを極小化 |
| 検認手続き不要 | 家庭裁判所での検認手続きを経ずに、速やかな相続手続きが可能 |
| 形式要件のチェック | 申請時に法務局職員が用紙サイズ・署名・押印等を確認(※内容の合法性は対象外) |
| 通知サービス | 遺言者の死亡情報を法務局が把握した場合、事前に指定した相続人等への通知も可能 |
| 低コスト | 1通3,900円で利用可能。公正証書遺言と比較して大幅に安価 |
| 相続税申告での活用 | 検認不要のため、相続税申告期限(10か月)内での手続きがスムーズ |
大手メディアでの扱い
| メディア | タイトル | 掲載日 | 要約 |
|---|---|---|---|
| 毎日新聞 | 費用3900円「自筆遺言書保管制度」の利用者増 円滑相続に期待 | 2023-03-03 | 制度開始から利用件数が増加。手数料3,900円で法務局が原本50年・画像150年保管。紛失・改ざん防止と検認不要で相続手続きが円滑化 |
| 名古屋テレビ(メ〜テレ) | 最後のメッセージを法務局が預かります 終活の一環、相続をスムーズに 自筆証書遺言書保管制度 | 2024-09-14 | 自宅保管による紛失・改ざんリスクを解消。制度の仕組み、公正証書遺言との違い・メリットを具体例で紹介 |
| 東洋経済オンライン | 「遺言書」が面倒くさい人こそ知るべき最新制度の恩恵 | 2025-04-30 | 遺言書作成をためらう人向けに制度概要とメリットを紹介。検認不要で手軽に確実な意思表示が可能と解説 |
| 朝日新聞(相続会議) | 遺言書作成が便利に 法務局に保管する制度とは? | 2024-02-21 | 紛失・改ざん防止、検認不要など制度の利点と利用方法をわかりやすく解説 |
4. 保管制度の利用方法を具体的に解説
4-1. 事前準備
| 必要書類・物品 | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 遺言書原本 | A4サイズ推奨(横書き・縦書き問わず)/ホチキス留め不可/封筒や封印は不要 |
| 住民票の写し | 本籍地記載・発行後3か月以内 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等(顔写真付き) |
| 収入印紙 | 3,900円分(法務局窓口で購入可能) |
| 予約番号 | 専用予約システムまたは電話で事前取得が必須 |
4-2. 自筆証書遺言の簡単な書き方(6ステップ)
| ステップ | 作業内容 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | 内容を事前検討 | 参考サイトで文例を確認し、相続財産と受遺者を整理 (※テンプレートは参考のみ・印刷利用は厳禁) |
| 2 | 本文を手書きで清書 | A4用紙に黒インクで縦・横書きどちらでも可。 行間は1行以上空けると読みやすい |
| 3 | 日付・氏名を自筆し押印 | 元号・西暦どちらでも可。 押印は実印推奨(認印でも法的に有効) |
| 4 | 財産目録を作成 | パソコン作成可。 各ページに署名・押印を忘れずに |
| 5 | ページ番号を振る | 「1/3」「2/3」…を余白に記入して抜け落ち防止 |
| 6 | ホチキス留めせず提出 | 法務局ではホチキス・封筒・封印は不要(原本確認のため) |
重要な注意事項
・遺言書本文は必ず全文手書き。テンプレートをそのまま印刷して使うと無効になる恐れがあります。
・清書前に専門家レビューを受けると形式・内容両面のミスを回避できます。
・付言事項(家族へのメッセージ)は最後にまとめて書くと読みやすく、気持ちも伝わりやすいです。
遺言書作成に役立つサイト
| サイト名 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 相続弁護士相談広場(Agoora) | 自筆証書遺言の書き方マニュアル~遺言書の例文ひな形と準備・作成のポイント | 法律監修あり。Word 形式テンプレートを無料配布。具体例付きで丁寧に解説。 |
| 司法書士柴崎事務所 | 遺言書の書き方を徹底解説:例文で簡単作成!Word ひな形付き | 司法書士による実務解説。状況別の文例が豊富で、Word ひな形を無料提供。 |
| デイライト法律事務所 | 自筆証書遺言(遺言書)のひな形|遺産別文例・テンプレート集 | 相続ケース別に詳細な文例とテンプレを掲載。オンライン作成ツールもあり実用性が高い。 |
4-3. 手続きの流れ
- 管轄法務局の選択(住所地・本籍地・不動産所在地のいずれか)
- 事前予約(必須) — オンラインまたは電話。希望日の 1 週間前までが目安
- 窓口での申請手続き — 申請書記入 ⇒ 形式確認 ⇒ 収入印紙3,900円納付
- 保管証の受領 — 保管番号と暗証番号を厳重管理
- 手続き完了 — 原本・画像が保管され 検認不要 に
4-4. 保管後の各種手続き
| 手続き内容 | 手数料 | 請求可能者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺言書閲覧(モニター) | 1,400円 | 遺言者本人のみ | 生前は本人のみ閲覧可 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1,400円/通 | 相続人・受遺者・遺言執行者等 | 相続開始後に請求可 |
| 遺言書の撤回・変更 | 撤回:無料 / 新規保管:3,900円 | 遺言者本人のみ | 新しい遺言書を保管すると従前の遺言書は失効 |
5. 制度利用時の注意点・よくある質問(FAQ)
Q:遺言書の内容を一部だけ修正できますか?
A:できません。 遺言書の内容を変更する場合は、全文を書き直して新たに申請する必要があります。
Q:本人以外が代理で申請できますか?
A:原則として本人の来庁が必要です。 身体的事情により来庁が困難な場合は、公正証書遺言を検討してください。
Q:保管中の遺言書を確認したい場合は?
A:事前予約+手数料 1,400円 で閲覧可能(本人のみ)。
Q:遺言者の死亡後、相続人への通知は?
A:事前指定があれば自動通知。 指定がない場合は相続人が証明書を請求します。
Q:オンライン申請はできますか?
A:2025年6月現在、来庁が必須(閲覧予約のみオンライン対応)。
Q:法務局で内容までチェックしてもらえますか?
A:形式要件のみ。内容確認は対象外のため、弁護士・司法書士にご相談ください。
重要な注意点
- 遺留分への配慮 — 法定相続人の遺留分を侵害すると後日請求を受ける可能性。
- 相続税への影響 — 内容によって税負担が変わる場合があるため税理士相談推奨。
- 遺言執行者の指定 — 複雑な相続では指定しておくとスムーズ。
6. 制度が向いている人・向いていない人
制度利用に向いている方
| 対象者 | 理由・メリット |
|---|---|
| 費用を抑えて確実に保管したい方 | 3,900円で長期保管+検認不要 |
| 自筆で自由に遺言書を作成したい方 | 公証人の関与なし・いつでも更新可 |
| 相続人が遠方に住む方 | 通知サービスで所在確認の手間を軽減 |
| 相続税申告が必要な方 | 検認不要で申告期限内手続きが円滑 |
制度利用に向いていない方
| 対象者 | 理由・代替案 |
|---|---|
| 来庁が困難な方 | 本人出頭が必須 → 公正証書遺言を検討 |
| 内容の法的有効性に不安がある方 | 法務局は内容をチェックしない → 専門家相談必須 |
| 複雑な財産構成・事業承継がある方 | 公正証書遺言+専門家サポートが適切 |
| 家族関係が複雑な方 | 紛争回避のため公正証書遺言の方が証拠力大 |
7. 最新情報(2025年6月現在)
制度の動向
- デジタル化の検討: 法務省がオンライン申請・電子遺言に向けた法整備を検討中(時期未定)。
- 手数料・様式: 現時点で変更予定なし。ただし将来改正の可能性あり。
利用状況
制度開始以降、利用件数は年々増加傾向にあり、終活への関心の高まりとともに注目を集めています。
8. まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の課題を解決する画期的な制度です。
- 安全・低コストで検認不要 — 3,900円で自筆証書遺言の弱点を解消
- 手続きは 4 ステップ — 予約 → 窓口提出 → 形式確認 → 保管証受領
- 本人出頭が必須 — 来庁が困難な場合は公正証書遺言も検討を
遺言書は相続トラブルを防ぐ重要なツールです。制度を活用する際は、内容面での不安があれば専門家にご相談いただき、ご自身とご家族にとって最適な相続対策をご検討ください。
資産全体を一括で整理したい方へ
相続準備をスマートに進める 「iNFINITY Life」 では、資産や思い出をまとめて管理できるクラウドサービスです。相続税のシミュレーションや具体的な相続対策を検討したい方も、 ぜひ下記リンクからご覧ください!
参考文献・出典
| 資料・メディア | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 法務省 | 遺言書保管制度 公式サイト | 2025-04 更新 |
*各記事は著作権法第32条に基づき、必要最小限の範囲で引用しています。詳細は出典元をご確認ください。
金融システムエンジニアとして20年以上、
大手金融機関向けシステム開発に従事した後、
現在は資産管理・相続に関する情報発信を行っています。
金融システムの現場で培った知識と、FP資格に基づく専門性を活かし、
複雑な税制や相続の仕組みを、公的資料に基づき正確かつ
わかりやすく解説することを心がけています。
【保有資格】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
証券外務員一種
応用情報技術者(AP)



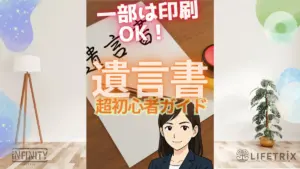
“遺言書を安全・確実に保管!自筆証書遺言書保管制度を徹底解説” に対して1件のコメントがあります。