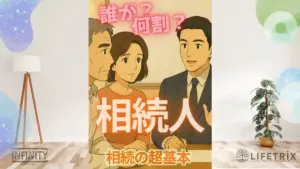海外資産の盲点—相続人を苦しめる5大リスクと最短対策ガイド
「父がアメリカに口座を持っていたらしい」—— 亡くなった後に初めてその事実を知ったものの、銀行からは英語の書類とプロベート※1 手続きの説明書が届き、どこから手を付ければよいのか分からない。
このように海外資産の存在すら把握していないケースは珍しくありません。放置すれば、凍結口座の維持手数料や外国税まで課され、数十万円から数百万円規模のコストが発生することもあります。
そこで本記事では「海外資産の盲点」をテーマに、代表的な5つのリスクと具体的な対策フローをまとめました。生前の備えや専門家との連携の参考にしてください。

はじめに
近年、海外に銀行口座、不動産、株式、暗号資産などを持つ方が増えています。しかし、相続人がその存在を知らないまま放置すると、口座凍結、名義変更の遅延、二重課税といった深刻な問題が生じる可能性があります。
本記事では、典型的なトラブル事例と対策、そして専門家に相談すべきポイントを分かりやすく解説します。
目次
【重要な免責事項】 本記事は 2025年7月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当方は責任を負いません。【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
1. 海外資産で発生しやすい5大リスク
相続人が海外資産の存在を知らない、あるいは手続きの複雑さに直面することで生じる主なトラブルは以下の通りです。
| リスク | 何が起こるか | 主なコスト | 手続き難易度 |
|---|---|---|---|
| 1. 海外銀行口座の凍結・休眠化 | 口座が凍結/休眠化し残高減少 | 現地弁護士費用・翻訳/公証費用 | ★★★★☆ |
| 2. 海外不動産の名義変更遅延 | 所有権不明・税滞納 | 不動産登記費用・現地税 | ★★★★★ |
| 3. 海外株式の換価困難 | 配当・通知が届かず現金化不可 | 証券会社手数料・弁護士費用 | ★★★☆☆ |
| 4. 暗号資産のアクセス不能 | 秘密鍵紛失で資産消失 | データ復旧費・税務コスト | ★★★★★ |
| 5. 二重課税・申告漏れ | 国を跨いだ相続税・罰則 | 追徴課税・加算税 | ★★★★☆ |
1-1. 海外銀行口座の凍結・休眠化
故人が海外に銀行口座を保有していた場合、死亡の事実が銀行に知らされると口座は凍結され、相続人がその存在を知らないままだと休眠口座化※5するリスクがあります。特に、情報提供に協力的でない銀行や、口座維持手数料によって残高が減少し、最終的にゼロになるケースもあります。
発生しうるコスト:
現地弁護士費用(数十万円〜数百万円)、情報開示請求費用、翻訳・公証費用、アポスティーユ※2取得費用
手続きの複雑さ:
非常に高い。現地での戸籍謄本や印鑑証明書の英訳・公証、アポスティーユ※2取得など複雑な手続きが必要になります。国によっては遺言検認手続き(プロベート※1)が必須となる場合もあります。
具体的事例:
アメリカでは、口座名義人が死亡すると口座が凍結され、裁判所を通じたプロベート※1手続きが必要になることがあります。この手続きには数ヶ月から数年を要し、弁護士費用も高額になる傾向があります[1]。シンガポールでも、現地の銀行口座の解約には裁判所命令が必要となる場合があります[2]。
1-2. 海外不動産の名義変更遅延
海外不動産の場合、その国の法制度に基づき所有権を確定し、名義変更手続きを行う必要があります。日本のように登記制度が明確でない国や、不動産売買・相続に関する手続きが複雑な国も多く、放置すると所有権が不明確になったり、現地の税金(固定資産税など)が滞納されたりする問題が生じます。
発生しうるコスト:
現地弁護士・司法書士費用(数百万円以上)、登記費用、各種税金(相続税、固定資産税、売却時のキャピタルゲイン税※8など)
手続きの複雑さ:
非常に高い。現地の法律専門家への依頼が必須であり、必要書類の収集、翻訳、公証、そして現地の税務申告など、多岐にわたる専門知識と手続きが必要です。
具体的事例:
フランスの不動産相続では、遺産に不動産が含まれる場合、遺産全体を登記簿に登録する手続きが必要です。日本とは異なる手続きや税金が課されるため、専門家の支援が不可欠です[3]。アメリカでは、プロベート※1手続きを経て、ようやく相続人への所有権移転が可能となります[4]。
1-3. 海外株式の換価困難
故人が海外の証券会社に株式や投資信託を保有していた場合、相続人がその存在を知らないと、配当金や償還金の所在が不明になったり、企業からの重要通知が届かなくなったりします。また、権利関係の複雑さから換価(現金化)が困難になることがあります。
発生しうるコスト:
現地証券会社との交渉費用、現地弁護士費用(数十万円〜数百万円)、税金
手続きの複雑さ:
高い。証券会社によっては、相続手続きに関する要件が厳しく、日本の戸籍謄本や相続関係書類の認証を求められることがあります。取引履歴の確認も難航する場合があります[5]。
具体的事例:
故人がアメリカ国籍保有者でなくてもアメリカ企業株式を保有していた場合、アメリカ法に基づく相続手続きが必要となり、複雑な書類作成や税務申告が求められます[6]。
1-4. 暗号資産のアクセス不能
暗号資産(仮想通貨)は、秘密鍵※10やウォレット※11のパスワードを故人しか知らない場合、相続人がアクセスすることが極めて困難になります。取引所によっては本人確認情報が不十分で相続人からの問い合わせに対応できない場合もあり、結果として資産が永遠に失われるリスクがあります。
発生しうるコスト:
専門家によるデータ復旧費用(成功保証なし、数十万円以上)、税務申告に関する追加費用、取引所との交渉費用
手続きの複雑さ:
非常に高い。法的枠組みが未整備な部分が多く、取引所ごとに異なる対応が求められます。秘密鍵※10やパスワードの喪失は、事実上資産を失うことを意味します[7]。
具体的事例:
故人が使用していたPCやスマートフォンのロック解除、パスワードの特定、取引所の特定とアカウント情報の確認など、技術的・法的なハードルが非常に高く、専門家でも対応が困難な場合があります[8]。
1-5. 二重課税・申告漏れ
日本は包括承継主義※3、アメリカは管理清算主義※4など、国によって相続法の原則が異なります。また、相続税(遺産税)の課税方式や税率も異なり、故人や相続人の居住地、国籍、資産の所在地によって適用される法律や税金が複雑に絡み合います。これにより、予期せぬ二重課税や申告漏れによる罰則のリスクが生じます。
発生しうるコスト:
追徴課税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税、現地での罰金(合計数百万円〜資産額の数割に及ぶ場合も)
手続きの複雑さ:
非常に高い。国際的な税務に詳しい税理士と現地弁護士の連携が不可欠です。租税条約の適用関係の判断も複雑です[9]。
具体的事例:
アメリカに資産がある場合、アメリカの遺産税の課税対象となる可能性があります。日米租税条約により二重課税は回避できるものの、申告義務は発生し、複雑な計算が必要となります[10]。また、日本の居住者で、総資産が5,000万円を超える場合、国外財産調書※6の提出義務があり、不提出や虚偽記載には罰則があります[11]。
2. トラブルを防ぐ3つの対策フロー
海外資産の相続トラブルを解決するためには、早期の情報収集と適切な専門家の活用が不可欠です。
2-1. 現地での手続き
情報収集の重要性
故人の遺品(手帳、PCデータ、メール、銀行からの郵便物など)から海外資産の手がかりを探します。可能な限り早く、関係機関(銀行、証券会社、大使館など)に問い合わせを行いましょう。
現地の法律専門家の選定
各国の相続法は日本と大きく異なるため、現地の法律に精通した弁護士や公証人を雇うことが不可欠です。特に、遺言検認手続き(プロベート※1)が必要な国では、現地弁護士なしに進めることは困難です。
必要書類の準備
日本の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを英訳し、外務省のアポスティーユ※2認証または大使館・領事館の領事認証を取得します。一部の国では宣誓供述書やサイン証明書なども必要となります。
2-2. 日本での申告・税務対処
相続税の申告 日本の相続税法では、被相続人・相続人の居住地や国籍に応じて、海外資産も課税対象となる場合があります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です[12]。
国外財産調書の提出 12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有している居住者は、翌年の3月15日までに「国外財産調書※6」を税務署に提出する必要があります[13]。
国際税務に強い税理士の活用 各国の相続税・遺産税と日本の相続税の調整(外国税額控除※7の適用など)、租税条約の確認、適切な資産評価など、専門的な知識が求められます。申告漏れや誤りがあると、加算税や延滞税が課されるため、必ず専門家に相談しましょう。
2-3. 専門家活用方法
国際相続には、日本の弁護士、税理士、司法書士、行政書士、そして現地の法律専門家など、多岐にわたる専門家の連携が不可欠です。
■各専門家の役割
日本の国際相続に強い弁護士
- 全体の手続きの統括・コーディネート
- 遺産分割協議の調整・紛争解決
- 現地弁護士との連携・交渉
- 複雑な法律問題の解決
国際税務に強い税理士
- 本の相続税申告・計算
- 国外財産調書※6の作成・提出
- 国際的な二重課税調整・外国税額控除※7の適用
- 現地税務専門家との連携
司法書士・政書士
- 日本での相続関係書類の収集・作成
- 戸籍謄本等の取得・整理、相続人調査
- 翻訳・公証・アポスティーユ取得支援
- 不動産登記手続き(日本国内分)
- 各種許認可申請の代行
- 現地機関との書類のやり取り
現地弁護士
- 現地の相続法に基づく手続き(プロベート※1、名義変更、口座解約など)
- 現地税務申告・納税
- 現地機関との交渉・法的代理
- 現地裁判所での手続き
■専門家選定のポイント
- 国際相続の実績が豊富か: 単に海外に支店があるだけでなく、実際に国際相続案件を多く手掛けているか確認しましょう。
- 提携する海外の専門家がいるか: 現地の信頼できる法律事務所や会計事務所とのネットワークがある専門家を選ぶとスムーズです。
- 費用体系が明確か: 事前に見積もりを取得し、追加費用が発生する可能性についても確認しておきましょう。国際相続の弁護士費用は、着手金と成功報酬の合算で数十万円から数百万円、税理士費用も資産規模に応じて数十万円から数百万円が目安となります[14, 15]。
- コミュニケーションが円滑か: 複雑な国際相続手続きでは、専門家との密な連携が重要です。質問に対して分かりやすく説明してくれる専門家を選びましょう。
3. よくある質問(FAQ)
Q1: 故人が海外資産を持っていたかどうかわかりません。どうすれば調査できますか?
A1: まず、故人の自宅やPC、スマートフォン内の遺品整理から手がかりを探しましょう。海外からの郵便物、メール、銀行口座の明細、証券会社の取引報告書、オンラインウォレット※11の履歴などがヒントになることがあります。海外の金融機関に直接問い合わせることも可能ですが、故人との関係性を示す公的書類の提出が求められます。調査が困難な場合は、国際相続に詳しい弁護士や調査会社に依頼することも検討してください。
Q2: 海外資産の相続に期限はありますか?
A2: 日本の相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。海外の相続手続きには、国によって時効や期限が定められている場合があります。例えば、アメリカではプロベート※1手続きに時間制限はありませんが、遺産税の申告期限が設けられています。期限を過ぎると罰金が課されたり、相続権を失ったりするリスクがあるため、判明次第速やかに対応を始めることが重要です。
Q3: 海外資産の相続で最も注意すべき点は何ですか?
A3: 最も注意すべきは、異なる国の法制度と税制度への理解不足です。日本の常識が通用しないことが多々あり、安易な自己判断はトラブルを深刻化させます。また、情報が断片的にしか得られないことが多いため、早めに国際相続の経験が豊富な専門家(日本の弁護士、税理士、そして現地の法律専門家)に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが肝要です。故人が生前に遺言書を作成し、海外資産についても明確に指定していれば、相続手続きは格段にスムーズになります。
Q4: 海外資産の相続で、どの専門家に最初に相談すべきですか?
A4: 一般的には、まず国際相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は全体の手続きを統括し、必要に応じて税理士、司法書士、行政書士、現地の専門家との連携を図ることができます。ただし、税務申告が主な問題である場合は、国際税務に強い税理士から相談を始めることも効果的です。
Q5: 海外資産の相続にかかる費用はどの程度ですか?
A5: 費用は資産の種類、所在国、金額によって大きく異なります。一般的な目安として、総費用は遺産総額の5-20%程度になることが多いです。日本の専門家費用(弁護士・税理士)で数十万円から数百万円、現地の専門家費用で同程度、その他翻訳・公証・税金等で数十万円が標準的な範囲です。事前に複数の専門家から見積もりを取得し、比較検討することが重要です。
4. 最新情報(2025年現在)
OECD暗号資産報告枠組み(CARF※9): 2026年実施予定。各国が取引所情報を自動交換し、暗号資産の申告漏れリスクが高まる見込み(2025年4月OECD声明)。
日本の国外財産調書制度: 2024年度税制改正で罰則が強化され、高額な過少申告加算税が追加されました。
デジタル相続の重要性: 暗号資産やデジタル資産の相続問題が急増しており、生前のデジタル遺言やパスワード管理の重要性が高まっています。
国際的な情報交換の強化: CRS(Common Reporting Standard)により、海外金融機関の口座情報が各国税務当局間で自動交換されるため、申告漏れのリスクが高まっています。
法改正動向は年度ごとに更新されるため、最新情報は国税庁や外務省サイトを必ず確認してください。
5. まとめ
海外資産の相続において重要なポイントは以下の通りです。
海外資産の最大の盲点は「存在を知らないまま放置」することにあります。銀行口座・不動産・株式・暗号資産の 5大リスク を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
現地手続きと日本の税務申告を並行して進めることで、時間的ロスを最小限に抑えることができます。
国際相続に強い弁護士・税理士の早期活用により、複雑な手続きを円滑に進めることが可能です。
生前の資産リスト化と遺言書整備により、相続人の負担を大幅に軽減できます。
専門家間の連携が成功の鍵となります。弁護士、税理士、司法書士、行政書士、現地専門家がそれぞれの専門分野で協力することで、スムーズな手続きが実現できます。
何よりも、専門家への早期相談が最も重要な対策となります。一人で悩まず、適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きを実現できます。
生前対策におすすめのサービス
海外資産を含む相続準備をスマートに——。 「iNFINITY Life」では、国内外の資産・思い出資産を一元管理。
まずは、資産の管理からはじめましょう
相続準備をスマートに進める 「iNFINITY Life」 では、資産や思い出をまとめて管理できるクラウドサービスです。相続税のシミュレーションや具体的な相続対策を検討したい方も、 ぜひ下記リンクからご覧ください!
用語解説
(※1)プロベート アメリカなどで遺言の有効性を確認し、遺産を清算・分配するために裁判所が監督する手続き。日本の家庭裁判所における相続手続きに相当しますが、より厳格で時間がかかります。
(※2)アポスティーユ ハーグ条約加盟国間で公文書の真正性を証明する外務省の付箋。追加の領事認証を省略できる国際的な認証制度です。
(※3)包括承継主義 被相続人の死亡と同時に、財産・債務がすべて相続人に直接移転する考え方(日本など)。
(※4)管理清算主義 裁判所が選任した遺産管理人(執行者)が遺産を管理・清算し、債務を弁済した後に残余を相続人へ分配する方式(米国など)。
(※5)休眠口座 長期間取引がない預金口座。日本では10年以上入出金がなく、最終的に預金保険機構へ移管される。海外では国により基準が異なります。
(※6)国外財産調書 12月31日時点で5,000万円超の国外資産を持つ居住者が翌年3月15日までに提出する書類。
(※7)外国税額控除 海外で支払った税金を日本の税額から差し引くことで二重課税を調整する制度。
(※8)キャピタルゲイン税 株や不動産などを売却して得た値上がり益に対して課される税金。
(※9)CARF OECDが策定した暗号資産の情報自動交換ルール(2026年実施予定)。
(※10)秘密鍵 暗号資産の所有権を証明し、取引を承認するために必要な暗号文字列。紛失すると暗号資産にアクセスできなくなる。
(※11)ウォレット 暗号資産を保管・管理するデジタル"財布"。取引所型(オンライン)、ソフトウェア型、ハードウェア型(オフライン)などがある。
参考文献・出典
[1] 米国の相続手続き(プロベート*1)に関する記述 栗林総合法律事務所. (2020年1月31日). 米国の相続手続き(プロベート*1). https://ks-kokusaisouzoku.jp/probate/
[2] シンガポールの相続法に関する記述 One Asia Lawyers. (2021年4月20日). シンガポール法律コラム:第19回 シンガポールの相続法について(2). https://oneasia.legal/15039
[3] フランスの不動産相続に関する記述 獨協大学 ジャック・コンブレ(フランス名誉公証人). (2011年). 相続処理におけるフランス 公証人の役割. https://dokkyo.repo.nii.ac.jp/record/470/files/P-095-D83h-98-6.pdf
[4] 不動産相続の新ルール(登記義務化とアメリカ税務)に関する記述 CDH. (2022年4月11日). 不動産相続の新ルール:登記義務化とアメリカ税務の落とし穴. https://www.cdhcpa.com/ja/不動産相続の新ルール:登記義務化とアメリカ税/
[5] 海外居住相続人の手続きに関する記述 マネックス証券. (2021年4月1日). 相続人が海外に居住している場合の手続きはどのようにすればよいですか?. https://faq.monex.co.jp/faq/show/304?categoryid=303&sitedomain=default
[6] 海外相続の環境に関する記述 三菱UFJ信託銀行. (2021年3月). 海外相続を取り巻く環境. https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbunreport01.pdf
[7] 仮想通貨(暗号資産)の相続手続きに関する記述 税理士法人トゥモローズ. (2022年6月26日). 【5分でわかる】仮想通貨(暗号資産)の相続手続きとポイントを解説. https://tomorrowstax.com/knowledge/2022062610470/
[8] 暗号資産のアクセス困難に関する記述 デジタルデータフォレンジック. (2024年3月29日). デジタル遺品のパスワード解除方法を事例付きで徹底解説. https://digitaldata-forensics.com/column/digital_properties/19726/
[9] 国際相続の相続税に関する記述 朝日新聞デジタル. (2022年4月11日). 国際相続の相続税はどうなる?. https://souzoku.asahi.com/article/15576737
[10] アメリカの相続税と国際相続に関する記述 名古屋総合法律事務所. (2023年6月28日). アメリカの相続税はいくらからかかる?国際相続の仕組みや日本との違いを解説. https://nagoyasougou.com/blog/blog/3799/
[11] 国外財産調書に関する記述 国税庁. (2024年4月1日現在). No.7456 国外財産調書の提出義務. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
[12] 相続税の申告と納税に関する記述 国税庁. (2024年4月1日現在). No.4205 相続税の申告と納税. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
[13] 国外財産調書制度に関する記述 FP協会. (2023年9月). 【No949】国外財産調書制度と公表資料について. https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no949/
[14] 国際相続の弁護士費用に関する記述 栗林総合法律事務所. (2020年1月31日). 弁護士費用 - 国際相続のご相談は、栗林総合法律事務所へ. https://ks-kokusaisouzoku.jp/fee/
[15] 国際相続コンサルティングに関する記述 税理士法人チェスター. (2024年4月1日現在). 国際相続コンサルティング|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. https://chester-tax.com/plan/international.html
金融システムエンジニアとして20年以上、
大手金融機関向けシステム開発に従事した後、
現在は資産管理・相続に関する情報発信を行っています。
金融システムの現場で培った知識と、FP資格に基づく専門性を活かし、
複雑な税制や相続の仕組みを、公的資料に基づき正確かつ
わかりやすく解説することを心がけています。
【保有資格】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
証券外務員一種
応用情報技術者(AP)