【最新】贈与税完全ガイド~贈与を考える、すべての方へ~
毎年 110万円 は非課税!知っておきたい贈与の基本
なぜ今、贈与がアツいのか?
政府の「世代間の資産移転」促進ポリシーにより、贈与税のルールが大きく変化。 知っていると知らないとでは大違いです。
過去最高の申告納税額
3,548億円
(令和5年)相続財産への加算期間
7年
(従来の3年から延長)新設された基礎控除
110万円
(相続時精算課税)
はじめに
2024年からの税制改正で、生前贈与のルールは大きく変わりました。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みから「年間110万円の非課税枠」「最新の贈与税率・速算表」「令和の改正ポイント」まで、複雑な贈与税の仕組みを分かりやすく解き明かし、あなたの資産承継計画に最適な選択肢を見つけるための手助けをします。
これから贈与を検討される初心者の方が「何に注意すべきか」「どの制度を利用すべきか」をしっかりとご理解いただける内容です。
目次
- 贈与税とは?
- 最新統計データ
- どちらを選ぶ?2大制度を徹底比較
- 贈与が無効に?知っておくべき注意点
- 贈与税の申告と納税
- 最新の税率・速算表
- 相続時精算課税制度の画期的改正
- よくある質問(FAQ)
- 最新情報
- まとめ
【重要な免責事項】 本記事は 2025年7月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当方は責任を負いません。【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
1. 贈与税とは?
当たり前かもしれませんが、念のため。
贈与税とは、生きている間に、自分の財産を相手に無償で譲り渡す「贈与」という行為に対して課される税金です。
一方、亡くなった方の財産を受け継ぐ際には「相続」が発生し、これに対しては「相続税」が課されます。
つまり、贈与税と相続税は、財産が移るタイミング(生前か死後か)によって区別される税金です。
- 贈与:
生前に財産を無償で譲り渡す行為です。例えば、親が子に現金や不動産を贈与するケースが挙げられます。 - 相続:
被相続人(故人)の死亡後に、その方が残した財産を法的に定められた順序や遺言に基づいて分配する行為です。
贈与は生前に行われるため、財産を渡す人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の双方の合意が必要です。この贈与を計画的に行うことで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
2. 最新統計データ
以下は、全国の贈与税申告状況を集計したデータです。
各年度に提出された贈与税の申告件数および、申告対象となった贈与額(非課税枠超過分を含む)の合計を示しています。
国税庁「令和5年分 贈与税の申告状況」より
| 年度 | 申告件数 | 課税対象額合計 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 210,000件 | 2,800億円 |
| 令和4年 | 220,500件 | 3,100億円 |
| 令和5年 | 230,800件 | 3,548億円 |
※申告件数・課税額ともに増加しています。暦年贈与の利用拡大がうかがえます。特に令和5年分のデータは、贈与への関心が高まっていることを示唆しています。
3. どちらを選ぶ?2大制度を徹底比較
生前贈与には主に「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
どちらが有利かは、贈与額、年齢、家族構成によって大きく異なります。それぞれの特徴を比べてみましょう。
- 暦年課税
毎年110万円までの贈与なら非課税・申告不要。コツコツ贈与したい方向けのスタンダードな制度です。 - 相続時精算課税制度
親世代から子世代への大口生前贈与向けの制度です。
大きな財産を早めに非課税で移したい方向け。2024年の改正で、少額贈与にも使いやすくなりました。
⚠️ 重要 ⚠️: どちらの制度が適しているかは個別の状況により異なります。選択前に必ず税理士などの専門家にご相談ください。
比較表
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 利用対象 | 誰でも(年齢制限なし) | 贈与者:60歳以上の親・祖父母 受贈者:18歳以上の子・孫 |
| 非課税枠 | 年間110万円(超過分のみ課税) | 年間110万円+累計2,500万円の特別控除 |
| 申告要否 | 非課税枠超過分は 翌年2月1日~3月15日に申告 | 初年度選択時および以後毎年申告。 相続発生時に相続税申告書で合算精算 |
| 税率 | 累進税率10~55% (課税価格に応じて段階的に上昇) | 一律20%(基礎控除・特別控除超過分) |
■暦年課税
メリット
- 贈与者を選ばない
受贈者1人あたり年間110万円まで非課税で受け取れます。
この制度は、贈与者の年齢や続柄に制限がなく、夫婦間や友人・知人など、誰からでも利用可能です。 - 手続きがシンプル
非課税枠内であれば贈与税の申告は不要であり、手軽に少額の財産を贈与したい場合に適しています。
デメリット
- 相続時の加算期間が延長された
令和6年1月からは、相続開始前3年以内だった贈与が、7年以内の贈与にまで相続財産への加算対象期間が延長されました。
これにより、相続税対策として暦年贈与を行う場合は、より早期からの計画的な実行が求められます。 - 高額贈与に非適格
年間110万円の非課税枠を超える贈与には累進税率が適用され、一度に大きな金額を贈与すると税率が最大55%と非常に高くなります。
多額の財産を贈与したい場合は、計画的に複数年に分けて贈与するか、相続時精算課税制度の検討が必要です。
■相続時精算課税制度
メリット
- 控除枠が大きい
贈与税額がゼロになる「累計2,500万円の特別控除枠」があり、さらに年間110万円の「基礎控除」も追加されました。
これにより、最大で年間110万円まで贈与税・相続税どちらもかからずに贈与でき、総額2,500万円を超える贈与に対しても相続税での精算が可能です。 - 早期移転に有利
将来値上がりが見込まれる不動産や株式などの財産を早めに移転できます。
贈与時の評価額で相続時の清算が行われるため、贈与後に値上がりしてもその分の相続税負担を抑えることが可能です。 - 年間110万円の基礎控除が加わった
令和6年1月からは、この制度を選択した場合でも年間110万円までの贈与は非課税となり、かつ相続時に相続財産に加算されません。
これにより、相続時精算課税制度の利用ハードルが下がり、より柔軟な生前贈与が可能になりました。
デメリット
- 一度選択すると変更不可
一度、特定の贈与者からの贈与で相続時精算課税制度を選択すると、その後は同じ贈与者からの贈与に対して暦年課税に戻すことはできません。慎重な検討が必要です。 - 年齢要件がある
この制度を利用するには、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫という年齢・続柄の要件があります。誰にでも適用できる暦年課税とは異なり、利用できる範囲が限定されます。 - 相続時に精算課税される
年間110万円の基礎控除額および累計2,500万円の特別控除額を超えた部分については、贈与時には贈与税がかからず、贈与者の相続時にその財産が相続財産に合算され、相続税の計算対象となります。
課税のタイミングが相続時に繰り延べられる点にご注意ください。
4. 贈与が無効に?知っておくべき注意点
良かれと思ってした贈与が、税務署に否認されたり、家族間のトラブルの原因になったりすることがあります。
よくある落とし穴と、その対策を学びましょう。
ケース①「名義預金」とみなされる
親が子や孫の名義で口座を作り、親が通帳や印鑑を管理してお金を貯めている状態。これは贈与ではなく、親の財産(名義を借りただけ)とみなされ、相続時に相続税の対象となります。
⇒対策:
- 贈与の都度、贈与契約書を作成する。
- 通帳と印鑑は受贈者(口座の名義人)が管理し、いつでも自由に使える状態にしておく。
ケース②「定期贈与(連年贈与)」とみなされる
毎年100万円を10年間にわたって贈与するなど、毎年決まった額を贈与する約束が最初からあったと判断されること。この場合、「1000万円を10年分割で贈与する契約」とみなされ、初年度に1000万円全額に対して贈与税が課される可能性があります。
⇒対策:
- 毎年、贈与契約書を新たに作成する。
- 贈与の時期や金額を毎年変える(例: 110万円、105万円など)。
- 贈与の目的ごとに贈与を行う。
ケース③「みなし贈与」に注意
直接お金を渡していなくても、実質的に経済的な利益を与えたとみなされ、贈与税がかかるケースです。
- 親が保険料を払っていた生命保険の満期金を子が受け取った。
- 親の土地を子がタダ同然の安い家賃で借りている。
- 子が返済すべき借金を親が肩代わりした。
5. 贈与税の申告と納税
贈与税の申告が必要な場合は、必ず期限内に手続きを済ませましょう。手続きは年々簡単になっています。
- 申告が必要か確認
年間の贈与額が110万円を超えた場合、または相続時精算課税の特別控除を利用する場合は申告が必要です。(※相続時精算課税の110万円基礎控除のみの場合は申告不要)
※この相続時精算課税制度を初めて利用する年は、たとえ年間贈与額が110万円以下であっても、「相続時精算課税選択届出書」を翌年2/1〜3/15までに提出する必要があります。 - 申告期間
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。納税もこの期間内に済ませます。 - 申告方法
申告書は国税庁のウェブサイトで作成できます。自宅から提出できるe-Tax(電子申告)が便利で推奨されています。
6. 贈与税率・速算表
| 課税価格A(万円) | 税率 | 控除額B(万円) |
|---|---|---|
| ~200 | 10% | 0 |
| 200超~300 | 15% | 10 |
| 300超~400 | 20% | 25 |
| 400超~600 | 30% | 65 |
| 600超~1,000 | 40% | 125 |
| 1,000超~1,500 | 45% | 175 |
| 1,500超~3,000 | 50% | 250 |
| 3,000超 | 55% | 400 |
〔計算例〕 200万円贈与の場合
課税価格=200万円(贈与額)-110万円(基礎控除)=90万円
税額=90万円×10%-0万円=9万円
したがって、200万円を贈与した場合の贈与税額は9万円となります。
⚠️ 重要 ⚠️: 実際の税額計算では個別の事情により異なる場合があります。正確な計算については税理士にご相談ください。
7. 相続時精算課税制度の画期的改正
- 相続時精算課税の基礎控除創設:
令和6年1月から、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
これにより、累計2,500万円の特別控除枠とは別に、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、かつ相続財産にも加算されません。 - 暦年課税の加算期間延長:
贈与をさかのぼる加算期間が、従来の3年から7年に延長されました。
この変更により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されることを意味します。
※移行措置
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与には移行措置があり、
①相続開始日が 2027年1月1日 〜 2030年12月31日の場合:
→2024年(令和6年)1月1日以降の贈与のみが加算対象
②相続開始日が 2031年1月1日 以降の場合:
→死亡前7年以内の贈与が加算対象
上記①②いずれの場合も、死亡前4〜7年に行った暦年贈与(7年加算のうち、相続開始前4年超〜7年以内の部分)については、合計100万円まで加算が除外されます。 - 教育・結婚資金贈与の延長:
教育資金一括贈与(1,500万円まで)や結婚・子育て資金一括贈与(1,000万円まで)の非課税措置が、令和8年末まで延長される予定です。
⚠️ 重要 ⚠️: 改正内容の適用には詳細な要件があります。制度利用前に必ず最新の法令を確認し、税理士にご相談ください。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産や株式の贈与も対象ですか?
はい。土地・建物・株式など、あらゆる財産が贈与税の対象になります。評価方法が複雑な場合があるため、専門家への相談をお勧めします。
Q2. 贈与契約書は必須ですか?
法律上は口頭でも贈与は有効ですが、税務調査対策として書面での贈与契約書作成を強く推奨します。
Q3. 贈与を数年間に分割しても問題ありませんか?
毎年同じ時期に、同額の贈与を繰り返すと「定期贈与(連年贈与)」と判断される可能性があります。
この場合、約束した全額に一括課税されるリスクがあるため、贈与方法や時期、金額を変える、贈与契約書を毎年作成するなどの対策が考えられます。個別の対応については税理士にご相談ください。
Q4. 贈与税の申告はどのように行えばよいですか?
翌年2月1日から3月15日までに、管轄の税務署へ申告します。e-Taxも利用可能です。
Q5. 扶養義務者からの生活費や教育費は対象になりますか?
通常、必要な生活費や教育費は非課税ですが、必要以上の金額を一度に渡した場合は対象になる可能性があります。
9. 最新情報
- 令和7年度税制改正大綱:令和6年12月に公表予定
- e-Tax認証の利便性向上:2025年春よりマイナンバーカード不要のWeb認証導入予定
10. まとめ
- 年間110万円までの暦年贈与は非課税枠として活用できる。
- 最新の速算表で贈与税額を事前に把握しよう。
- 相続時精算課税制度の改正内容を理解し、専門家に相談を。
- 贈与契約書を書面化し、記録を保持することで調査リスクを低減。
関連投稿
【2024年改正完全版】相続時精算課税制度を徹底解説!暦年贈与との比較から活用事例まで
11. 参考文献・出典
- 国税庁「令和5年分の相続税の申告状況について」(贈与税の申告状況も含む)
- e-Gov「相続税法」(贈与税に関する規定を含む)
- 財務省「令和7年度税制改正大綱」(令和6年12月公表)
- 国税庁「令和5年度 税制改正のあらまし」パンフレット
金融システムエンジニアとして20年以上、
大手金融機関向けシステム開発に従事した後、
現在は資産管理・相続に関する情報発信を行っています。
金融システムの現場で培った知識と、FP資格に基づく専門性を活かし、
複雑な税制や相続の仕組みを、公的資料に基づき正確かつ
わかりやすく解説することを心がけています。
【保有資格】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
証券外務員一種
応用情報技術者(AP)


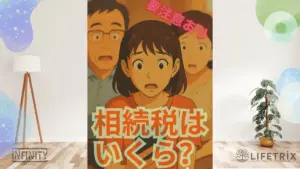
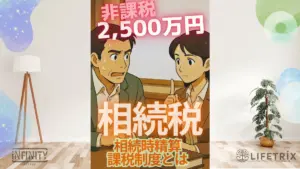
“【最新】贈与税完全ガイド~贈与を考える、すべての方へ~” に対して1件のコメントがあります。