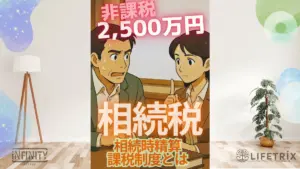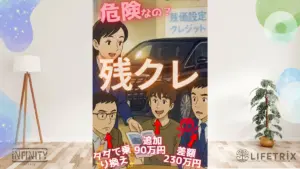認知症トラブルと備え:今からできる家族を守るための制度と手続き
口座凍結・特殊詐欺・デジタル資産
~家族を守るために今できる制度と手続き~
誰もが直面しうる現実
日本の高齢化に伴い、認知症は特別な病気ではなくなりました。統計データは、この課題が社会全体で取り組むべきものであることを示しています。
約8人に1人
2022年時点の65歳以上の有病率 (12.3%)
1,000万人超
軽度認知障がい(MCI)を含む患者数
215兆円
2030年に認知症の人が保有する金融資産 (推計)
日本の超高齢社会において、認知症は決して他人事ではありません。判断能力の低下は、特殊詐欺や銀行口座の凍結など、家計と生活の根幹を揺るがすトラブルに直結します。本記事では、公的資料等に基づき、実際に起こりやすい金銭トラブルの仕組みと、成年後見・任意後見・家族信託・銀行サービス、さらには見過ごされがちなデジタル資産の備えまでを、分かりやすく解説します。

目次
- 認知症トラブルの現状(統計・代表事例)
- 「口座凍結」の仕組みと解除までの流れ
- 備えの選択肢:成年後見・任意後見・家族信託・銀行サービス
- デジタル資産(ネット銀行・SNS・暗号資産)への備え
- 見守りと予防(チェックリスト・地域連携)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ(要点)
【重要な免責事項】 本記事は 2025年8月時点 の法令・制度に基づく一般的な解説です。今後の法改正や個別事情によって取り扱いが変わる可能性があります。地域や各窓口の運用も異なるため、最終的な判断や申請手続きは必ず 弁護士・司法書士・税理士などの専門家 へご相談ください。
本記事の内容に基づく判断により生じた損害について、当方は責任を負いません。【重要な注意事項】 本記事では分かりやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています。読者の資産状況・家族構成によっては別の方法が適切な場合があります。
認知症トラブルの現状とリスク
日本は世界でも有数の高齢化社会です。2022年時点での認知症患者数は約443万人で、65歳以上の人口の約8人に1人(有病率12.3%)に達しています。軽度認知障がい(MCI)を含めると、患者数の合計は1,000万人を超え、高齢者の3~4人に1人の割合に上ります。
将来推計では、2030年には認知症の人が保有する金融資産が215兆円、2040年には認知症患者数が約584万人(2022年から141万人増)に達すると予測されています。この規模の拡大により、金銭トラブルのリスクは今後さらに深刻化すると考えられます。
頻発する2つの代表的なトラブル
- 特殊詐欺:
高齢者を狙った還付金詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺は、認知件数・被害額ともに増加傾向にあります。2023年の特殊詐欺被害額は452.6億円、既遂1件あたりの平均被害額は243.8万円でした。2024年には全国で被害額が700億円を超え、過去最悪を記録するなど、被害は拡大の一途をたどっています。 - 金融資産の「口座凍結」:
本人の判断能力低下が疑われると、金融機関は本人の財産保護を目的として、銀行口座の取引を制限(事実上の凍結)する場合があります。これにより、たとえ家族であっても、生活費や介護費用を引き出せなくなるリスクが生じます。
認知症高齢者特有の被害の特徴
国民生活センターのデータによると、認知症等の高齢者の消費生活相談の約8割が家族など本人以外から寄せられており、被害に遭っているという認識が低い傾向にあります。また、平均契約購入金額や平均既支払額が高齢者全体よりも高額になる傾向があり、訪問販売や電話勧誘販売による被害が多いという特徴もあります。
「口座凍結」の仕組みと解除までの流れ
銀行が本人の認知症や判断能力低下を把握した場合、金融機関は本人の財産保護義務を果たすため、口座取引を停止(実質的に凍結)します。これは詐欺被害や不正利用を防ぐための重要な措置ですが、家族にとっては予期せぬ困難を生み出します。
口座凍結の解除方法
この凍結を解除し、預金を引き出すための唯一の法的解決策は成年後見制度の利用です。家庭裁判所への成年後見人選任の申立てから実際に後見人が選任されるまでには、通常3〜4ヶ月の期間を要します。
この期間中、口座は凍結されたままであるため、急な医療費や介護費用などの出費に対応できない可能性があります。最高裁判所事務総局の統計でも、「預貯金の管理・解約をするため」が成年後見人選任の申立て動機として最も多いことが報告されています。
後見制度開始後の注意点
- 後見制度が開始された後は、成年後見人が本人の財産管理や身上監護(医療・介護に関する契約など)を行います。
- ただし、居住用不動産の売却など特定の重要な行為については家庭裁判所の許可が必要となります。
- また、成年後見人の報酬として月額2~5万円程度が本人の死亡まで継続して必要になります。
備えの選択肢:制度とサービスの要点
認知症に備えるための制度やサービスはいくつかあります。それぞれの特徴を理解し、自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
1. 成年後見制度(法定後見)
- 概要: すでに判断能力が低下した方を対象に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や身上監護を行う公的な制度です。
- メリット:
- 本人の財産を法的に強力に保護できる
- 詐欺被害などによる契約を取り消すことができる
- 第三者(専門職)が後見人になる場合、中立的な財産管理が期待できる
- デメリット:
- 手続きに時間と費用がかかる(報酬例:月2〜5万円程度が死亡まで継続)
- 一度開始すると原則として本人の判断能力が回復しない限り終了できない
- 財産管理に柔軟性が制限される場合がある
2. 任意後見制度
- 概要: 本人が元気なうちに、公正証書で将来後見人となる人や業務範囲を契約しておく制度です。
- メリット:
- 本人の意思を最大限に反映できる
- 信頼できる人に後見人を任せられる
- 契約内容を自由に定めることが可能
- デメリット:
- 実際に効力が発生するには、本人の判断能力喪失後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任する必要がある
- 任意後見監督人への報酬も発生する
3. 家族信託(民事信託)
- 概要: 元気なうちに財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・承継の方法を定めておく私的な契約です。
- メリット:
- 裁判所を介さず、柔軟かつ迅速な財産管理が可能
- 不動産の売却や賃貸といった資産活用も行いやすい
- 二次相続(次の世代への承継)まで指定できる
- デメリット:
- 契約締結には本人の明確な判断能力が必須条件
- 身上監護(医療・介護契約など)は行えない
- 濫用のリスクがあるため、慎重な意思確認が必要
4. 銀行の高齢者向けサービス
各金融機関で提供されているサービスには以下のようなものがあります:
代理人カード
- 概要: 本人名義の預金口座から代理人がATMで入出金・振込みを行えるサービス
- メリット: 手続きが簡単で、手軽に始められる
- デメリット:
- 機能がATMでの取引に限定される
- 認知症が進行すると金融機関の判断で利用停止となる可能性がある
- 高齢者のATM利用上限額が10~20万円程度に制限される場合がある
信託・見守りサービス(例)
- 三菱UFJ銀行: 代理出金機能付信託「つかえて安心」(初期費用:信託金額の1.1~1.65%、月額528円)
- 三井住友銀行: SMBCエルダープログラム(月額9,900円、普通預金口座に1,000万円以上の預け入れが条件)
- ゆうちょ銀行: みまもり訪問サービス(月額2,500円)、みまもりでんわサービス(月額1,070円/1,280円)
デジタル資産への備えの必要性
現代では、オンライン上の各種アカウントや暗号資産など「デジタル遺品」への対策も重要になっています。本人が認知症になったり亡くなったりすると、IDやパスワードが不明なため、家族でも解約・相続・削除手続きが困難になるケースが少なくありません。
主要サービスの対応
- LINE: 一身専属のサービスのため、遺族が引き継ぐことはできません。アカウント削除を希望する場合は、LINEの問い合わせフォームから依頼が必要です。
- Google: 「アカウント無効化管理ツール」を提供しており、生前に設定しておくことで、一定期間アカウントが使用されない場合に指定した連絡先に通知したり、アカウントを削除したりできます。
- Apple: 「故人アカウント管理連絡先」機能により、事前に指定した人物が故人のApple IDアカウントとデータにアクセスできるようになります。
- 暗号資産: 相続は可能ですが、各取引所(bitFlyer、GMOコイン、DMM Bitcoinなど)の所定の手続きと法定相続情報証明、遺産分割協議書などの書類提出が求められます。残高は相続開始時点で日本円に換算されて支払われることが多いです。
デジタル終活の具体的な準備
- デジタル資産のリストアップ: アカウント名、ID、パスワード、登録メールアドレスなどを整理
- パスワード管理ツールの利用: セキュリティを保ちつつ、家族がアクセスできる方法を検討
- 家族への情報共有: エンディングノートや遺言書に記載
- プラットフォームの継承設定: Google、Appleなどの事前設定を活用
見守りと予防の重要性
認知症トラブルの最も有効な対策は、早期発見と予防です。
早期発見のためのチェックポイント
認知症の初期症状は物忘れに留まりません。以下のような変化に注意が必要です:
- 記憶・認知機能: 物忘れの頻度増加、同じ話の繰り返し、日付や曜日の間違い、言葉が出てこない
- 日常生活の変化: 金銭管理や買い物の困難、外出への不安、家事の不手際、身なりの乱れ、ゴミの分別間違い、郵便物の滞留
地域社会と専門機関による支援体制
- 地域包括支援センター:
高齢者の生活全般に関する総合相談窓口として、地域住民や民間事業者と連携した見守りネットワークを構築 - 金融機関の取り組み:
- 高額の払戻し等を行う高齢顧客への声かけ
- 不審な取引があった場合の警察への通報
- ATMでの振込・引出限度額の制限
- 警察の詐欺防止対策:
- 自動録音機器の無償貸与や購入補助
- 特殊詐欺に関する継続的な注意喚起
よくある質問(FAQ)
Q1. 親の口座が使えなくなった場合、どうすればいいですか?
A. 銀行が認知症を疑い口座を凍結した場合、成年後見人の選任が必要です。
手続きは以下の通りです。
①家庭裁判所で成年後見人選任の申立てを行う(申立書、医師の診断書、戸籍謄本等が必要)。
②審理期間3〜4ヶ月後に、後見人が選任される。
③選任された後見人が銀行で口座凍結解除手続きを行う。
なお、後見人が選任されるまでの間は、他の資金源で対応が必要です。
Q2. 成年後見制度を利用した場合、自由に不動産を売却できますか?
A. 居住用不動産の売却など重要な行為については、家庭裁判所の許可が必要です。また、後見人は被後見人の利益を最優先に行動する義務があります。
Q3. 任意後見はいつから効力が出ますか?
A. 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に効力が発生します。監督人選任の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが行えます。
Q4. 家族信託で注意すべき点は?
A. 契約時には本人の明確な意思能力が必要です。濫用を防ぐため、第三者による意思確認、公正証書の作成、医師の診断書取得などの慎重な手続きが推奨されています。
Q5. 暗号資産は相続できますか?
A. 相続は可能ですが、パスワード等が不明だと困難です。
手続きの流れは以下の通りです。
①各取引所に電話で相続手続きを依頼する。
②法定相続情報証明書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等を準備する。
③取引所指定の相続手続書類に記入・提出する。
④審査完了後、日本円で相続人口座に振り込まれる。
生前にアクセス情報を家族に共有しておくことが重要です。
Q6. 代理人カードがあれば認知症対策は十分ですか?
A. 代理人カードは手軽な手段ですが、認知症が進行すると金融機関の判断で利用停止となる可能性があります。より包括的な対策として、任意後見や家族信託などとの組み合わせを検討することをお勧めします。
まとめ(要点)
- 特殊詐欺と口座凍結は、認知症に伴う最大の金銭的リスクです。2024年の特殊詐欺被害額は700億円を超え、過去最悪を記録しました。
- トラブル発生後、口座凍結の解除には成年後見人の選任が必要となり、通常3〜4ヶ月の期間と継続的な報酬支払いが必要です。
- 任意後見、家族信託、銀行サービスはそれぞれ特徴が異なり、状況に応じて組み合わせることで対応範囲を広げることができます。重要なのは、本人の判断能力があるうちに準備することです。
- デジタル資産の一覧化と継承設定は、現代において必須の対策です。Google、Appleなどの事前設定機能を活用し、家族への情報共有を行いましょう。
- 日頃からチェックリストを活用し、地域と連携することで、早期発見と予防につながります。地域包括支援センターは重要な相談窓口です。
- 法改正の動向にも注意が必要です。成年後見制度については、期間設定や役割分担を可能とする見直しが議論されており、より利用しやすい制度への変更が期待されています。
認知症対策は、単一の制度に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせた多角的なアプローチが重要です。専門家(弁護士、司法書士、税理士、金融機関など)に相談し、個々の家庭状況に最適な対策を講じることをお勧めします。
今日からできる“認知症トラブル”対策
iNFINITY Lifeで資産を一元リスト化。元気なうちに家族と共有して、口座凍結や手続き遅延に備えましょう。
※認知症の予防・改善を目的としたサービスではありません。
参考文献・出典
公的機関・金融機関
- 警察庁「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等(確定値)」(PDF) (2024年3月14日)
- 警察庁「特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(統計・資料集)」 (2024年4月22日)
- 裁判所|後見ポータル「成年後見制度について」 (2024年5月10日)
- 東京家庭裁判所「申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)」 (2024年5月10日)
- 全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料の作成について」 (2020年3月26日)
- 消費者庁『消費者白書 2023』第1部第2章第2節「高齢者の消費者トラブル」 (2023年5月26日)
- 国民生活センター「65歳以上の消費生活相談の状況(発表情報)」 (2024年5月22日)
- 内閣府『令和6年版 高齢社会白書』「認知症高齢者数等の推計」 (2024年6月14日)
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)(概要)」 (2015年1月27日)
- 法務省『犯罪白書』 (最新版は2024年4月発行)
デジタルサービス・企業
- Google アカウント「アカウント無効化管理ツールについて」 (2023年10月4日)
- Apple サポート「故人アカウント管理連絡先を追加する方法」 (2023年12月14日)
- Apple サポート「亡くなったご家族のApple Accountへのアクセスを申請する方法」 (2023年12月14日)
- LINE セーフティセンター「故人のアカウントを閉鎖する(ご遺族の手続き)」 (2022年4月11日)
金融システムエンジニアとして20年以上、
大手金融機関向けシステム開発に従事した後、
現在は資産管理・相続に関する情報発信を行っています。
金融システムの現場で培った知識と、FP資格に基づく専門性を活かし、
複雑な税制や相続の仕組みを、公的資料に基づき正確かつ
わかりやすく解説することを心がけています。
【保有資格】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
証券外務員一種
応用情報技術者(AP)